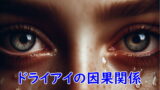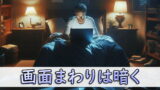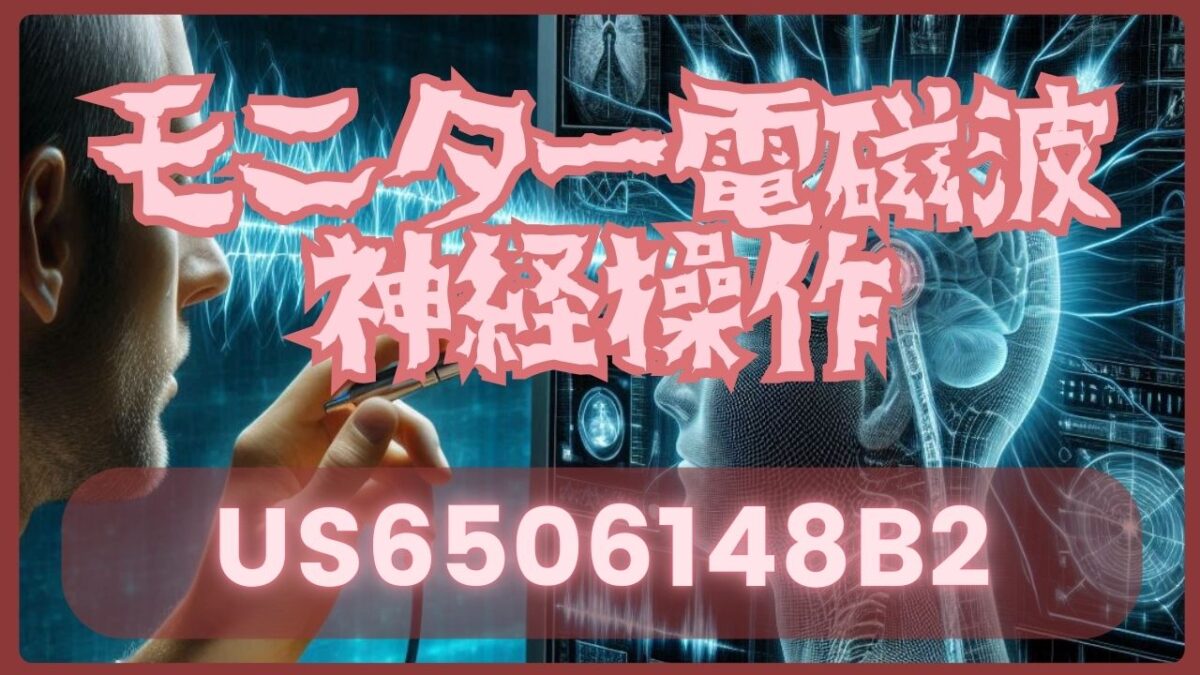ドライアイは予防と改善ができる
小学生の頃からパソコン(当時はマイコン)を使い、ゲーセンの店員、大型コンピューターのオペレーター、そしてWEBコンサルタント。画面を見続け40年以上の私。
30年前にはドライアイというものかもと、東京病院(現:花と森の東京病院)にて診断。
目薬は常に2つキープしていた私でも、今では目薬1滴も使いません。
理由はドライアイの原因を調べて、予防法を実践したから。
その根拠と実践ノウハウをまとめましたので、参考にしてください。
ご質問などあれば、SNSなどから私「桑野一哉」を探してメッセージくださいな。
ドライアイの原因
ドライアイのはじまりは1975年くらいから。
国際基準が作られたのは、1995年からだそうです。
つまり50年くらい前には存在しなかった症状。
風で目が乾くとか、まぶたを開くとか言われていますが怪しい。
1970年より前に、風もあるしまぶたを開くことはあったでしょ、つまりウソ。
では本当の原因はなんだと思いますか?
ドライアイの予防法
ドライアイの原因がわかれば、あとは対策をするだけ。
そうは言ってもドライアイになる人が増えるのは、そのような環境。
ドライアイになる条件を排除することが、最高の予防法です。
ドライアイの因果関係
原因と言われる風やまばたき説のおかしさを解説。
眼科医でもオフィスワークをしているわけではありません。
本当の因果関係を理解すると、目の疲れを避けることができますよ。
ドライアイの原因は凝視
まばたきをしないから目の表面が乾く。
これは原因ではなくて、結果です。
ではなぜ瞬きをしなくなるのか?
本当の原因は凝視だからです。
画面周りを暗くする
パソコンなどのモニターを見る場合は周りを暗くすること。
厚労省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」2019年の改訂では、「画面周りは500ルクス以下」という記述が削除されています。しかしグレアはそもそも「まぶしさ」ですから暗くする必要があるわけです。
モニターの適正距離
人間の眼球は、近くを見続けるようにはできていません。
厚労省の基準では40cm以上が目安ですが、離れるほど目の負担は少なくなります。
オフィスでは難しいでしょうが、自宅のテレワーク環境なら可能でしょう。
文字を大きくする
これは凝視対策ですが、ぱっと見てわかると認知負荷が少なくて済みます。
脳が疲れにくい、ということですね。
スマホやタブレットでは物理的な大きさの制限があります。
作業をするならパソコンで大画面を離れて見ましょう。
モニターの最適な高さ
厚労省は「画面の上端は眼の高さまで」としていますが、低いかなと思います。
特にディスプレイが近いと、下を向いて作業をしてしまうから。
私の環境では、2m離れて目線は画面の中央ですね。
猫背防止のためにも、画面の下向きはおすすめしません。
これらがドライアイの予防対策です。
20年の実績はあるので、ぜひとりいれてみてください。
情報機器作業における労働衛生 管理のためのガイドライン